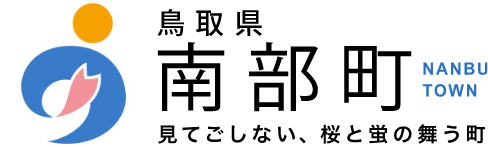限度額適用認定証
1か月に1つの医療機関で、自己負担額限度額を超える診療を受けるときは、医療機関に「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」を提示すると、保険適用分の医療費の窓口支払額が自己負担限度額までとなります。
あらかじめ国保の窓口での申請が必要で、国保世帯の所得に応じて交付されます。
手続きに必要なもの
- 限度額適用認定証の交付を受ける方の保険証
- 来庁される方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
ご注意ください
- 70歳以上の方で「現役並み所得者Ⅲ」「一般」の区分の方は保険証兼高齢受給者証の提示により、医療機関での窓口負担額は自己負担限度額までとなり、限度額証が必要ないため、交付しません。
- 同じ世帯の国民健康保険に加入されている方が住民税の申告をしていない場合は、所得区分を決定できないため交付ができません。
- 70歳未満で国民健康保険税を滞納している場合は、限度額適用認定証を交付しません。(「オ」の方には食事の減額認定証を交付します)なお、既に納付いただいていて町で確認が取れない場合、納付いただいたことがわかる領収書等の提示をお願いする場合があります。
- 「マイナ受付」ができる医療機関等で受診する場合、窓口においてマイナンバーカード又は健康保険証のみを提示し、ご本人の情報提供に同意することで、自己負担額までとなり役場での限度額適用認定証の申請手続きが不要となります。(※ただし、70歳未満「オ」の区分の人、70歳以上「低所得者Ⅱ」の区分の人で、過去12カ月の入院日数が90日を超える人は、限度額証の交付申請が必要です。)