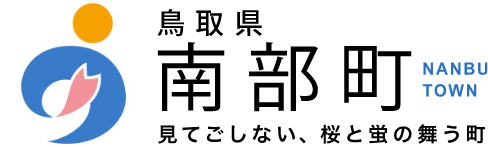個人町民税について
課税の対象者
個人町民税は、1月1日現在で町内に住所があり、前年中に一定額以上の所得があった方に所得割と均等割が課税されます。町内に住所はないが、事務所・事業所・家屋がある方に均等割が課税されます。
個人町民税の税率
均等割
均等割の税率は次のとおりです。
令和5年度まで
- 町民税 年額3,500円
- 県民税 年額2,000円※県民税には「豊かな森づくり協働税」500円を含みます。
令和6年度から
- 町民税 年額3,000円
- 県民税 年額1,500円※県民税には「豊かな森づくり協働税」500円を含みます。
所得割
所得割の税額は一般に次のような方法で計算されます。
課税標準額(前年中の所得金額-所得控除額)×税率-税額控除=所得割
納付方法
個人町民税は個人県民税とあわせて納付することになっており、次の3つの方法があります。
(一般的に個人町民税と個人県民税をあわせて個人住民税といいます)
普通徴収
納付書、口座振替で直接納めていただくものです。例年6月、8月、10月と翌年の1月の4回に分けて納めていただきます。
給与からの特別徴収
市区町村から給与の支払者を通じて通知され、給与の支払者が毎月の給与の支払の際にその人の給与から税金を引き落として、これを翌月の10日までに市区町村に納入することになっています。
例年6月から翌年の5月までの給与から差し引いて、給与の支払者が納付します。
公的年金からの特別徴収
65歳以上の公的年金受給者の年金所得に係る住民税は、税額決定通知書により、市区町村から通知され、公的年金の支払者が年金の支払の際にその人の年金から引き落として、これを翌月の10日までに市区町村に納入することになっています。
公的年金からの特別徴収は、年6回(偶数月)の公的年金の支払の際に行われ、4月、6月および8月には、その年の2月に徴収された額と同額が、10月、12月および翌年2月には、その年度の住民税額から4~8月に徴収された額を差し引いた残りの税額の3分の1ずつが、徴収されます。
なお、新たに公的年金から特別徴収の対象となっている方については、通常、その年度の住民税額の2分の1に相当する額が普通徴収され、10月~翌年2月において残りの税額について特別徴収されることになります。
町民税が課税されない人
均等割と所得割のいずれも課税されない方
ア) 生活保護法によって生活扶助を受けている方
イ) 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下(給与年収に直すと、204万4千円未満)の方
均等割の課税されない方
前年中の合計所得金額が次の金額以下の方
- 扶養親族がいない方 38万円
- 扶養親族がある方
28万円×(本人+同一生計配偶者・扶養親族の人数)+16万8千円+10万円
所得割の課税されない方
前年中の総所得金額等(合計所得金額に純損失や雑損失などの繰越控除を適用して計算した金額)が次の金額以下の方
- 扶養親族がいない方 45万円
- 扶養親族がある方
35万円×(本人+同一生計配偶者・扶養親族の人数)+32万円+10万円