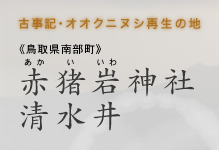古事記をめぐる旅
山陰の古事記ゆかりの地を旅してみませんか。
施設紹介
|
[1]茅部神社(かやべじんじゃ)~天の岩戸散策
高天原伝説は全国何か所か存在しますが、ここ岡山県の蒜山(ひるぜん)もその一つです。茅部神社は、古くは天磐座といわれた歴史ある社で、近くに天岩戸、真名井の滝、天の浮橋などがあります。茅部神社の参道にそびえる13mもの明神型石鳥居は日本一の規模を誇ります。春には神社までの約1kmの参道を、美しい桜並木が彩ります。
[2]塩釜の冷泉(しおがまれいせん)
蒜山(ひるぜん)三座の真中、中蒜山(1,122m)の裾の谷間から湧き出る天然水。湧水は、東西12m、南北5m、面積約60m2のひょうたん池を形成し、最深部は 1.9m、湧水量は毎秒300リットル、水温は年中11度前後と冷たいことからも冷泉という名の意味がよくわかります。昭和60年には日本名水百選(環境庁)に認定。地元塩釜奉賛会が中心となって管理し、今も変わらず村内の約600世帯の生活用水として受け継がれています。(※但し現在は取水禁止)
[3]大山桝水高原(だいせんますみずこうげん) 天空リフト
[6]赤猪岩神社・清水井・母塚山
大国主(オオクニヌシ)が命を落とし、母の愛と二人の女神の力で生き返った「再生神話」の地が、鳥取県南部町の赤猪岩神社(あかいいわじんじゃ)です。境内には大国主が抱いて落命したとされる大岩が封印されています。神社近くには、大国主蘇生のために使われた水が湧く清水井(しみずい)があります。また、イザナミ御陵との言い伝えのある母塚山からは、中国山地の山々から大山、島根半島から日本海まで大パノラマの絶景が楽しめます。
赤猪岩神社 https://www.town.nanbu.tottori.jp/akaiiwa/3/1/
清水井 https://www.town.nanbu.tottori.jp/akaiiwa/3/2/
母塚山 https://www.town.nanbu.tottori.jp/akaiiwa/3/4/
赤猪岩神社 https://www.town.nanbu.tottori.jp/akaiiwa/3/1/
清水井 https://www.town.nanbu.tottori.jp/akaiiwa/3/2/
母塚山 https://www.town.nanbu.tottori.jp/akaiiwa/3/4/
[8]美保神社 青石畳通り
大国主(オオクニヌシ)の第一の御子神コトシロヌシが祀られています。コトシロヌシの別名はえびす様。美保神社は、全国のえびすさまの総本社と言われる古社です。毎年12月3日に行われる諸手船神事は、コトシロヌシが釣りをしていたところに国譲りの可否を問うために使者が船に乗ってやってきたという国譲り神話をなぞらえたものです。
美保神社から仏谷寺を結ぶ約250mの青石畳通りは、雨の日にうっすらと青色に変化することからその名がついたと言われており、与謝野鉄幹・晶子夫妻、高浜虚子などの文豪が多く訪れた由緒正しい旅館、旧家が並んでいます。その一角に構える太鼓醤油店の地醤油は、かの北大路魯山人もその味を絶賛したという老舗です。
美保神社から仏谷寺を結ぶ約250mの青石畳通りは、雨の日にうっすらと青色に変化することからその名がついたと言われており、与謝野鉄幹・晶子夫妻、高浜虚子などの文豪が多く訪れた由緒正しい旅館、旧家が並んでいます。その一角に構える太鼓醤油店の地醤油は、かの北大路魯山人もその味を絶賛したという老舗です。
[9]古代出雲王陵の丘
国指定史跡、全国最大の方墳・造山古墳群を中心に、荒島地域は大型古墳ゾーンとして有名で、この周囲一体を公園として整備したのが、古代出雲王陵の丘です。標高約50mの丘からは、中海をはじめ遠くには島根半島を一望することができます。
[10]八重垣神社(やえがきじんじゃ)
「早く出雲の八重垣様に、縁の結びが願いたい」という出雲の古い民謡の一節からもわかるとおり、八重垣神社は出雲の縁結びの大神として知られています。スサノオが大蛇を退治する間に、イナタヒメ(稲田姫命)が身を隠していたとされています。
大蛇から身を隠していたイナタヒメが日々の飲み水とし、また姿を写す鏡としていたという言い伝えがある「鏡の池」では、和紙に硬貨を乗せて池に浮かべ、和紙の沈む速さで良縁の訪れを占う良縁占いが人気です。
大蛇から身を隠していたイナタヒメが日々の飲み水とし、また姿を写す鏡としていたという言い伝えがある「鏡の池」では、和紙に硬貨を乗せて池に浮かべ、和紙の沈む速さで良縁の訪れを占う良縁占いが人気です。
[11]熊野大社
出雲大社とともに、出雲国一の宮として知られています。火の発祥の神社として、「日本火出初之社」(ひのもとひでぞめのやしろ)とも呼ばれています。
熊野大社公式HP http://www.kumanotaisha.or.jp/
熊野大社公式HP http://www.kumanotaisha.or.jp/
[12]須我神社(すがじんじゃ)
古事記によると、スサノオは八岐大蛇を退治した後、妻のイナタヒメ(稲田姫命)とともに当地に宮殿を建て鎮まったとされています。美しい雲の立ち昇るのを見たスサノオが、「八雲立つ 出雲八重垣 つまごみに 八重垣つくる この八重垣を」と日本で一番古い歌を歌ったとされ、「和歌発祥の地」とも伝えられています。
[13]加茂岩倉遺跡(かもいわくらいせき)
島根県雲南市(うんなんし)にある弥生時代の集落で、国の史跡に指定されています。日本最多となる39口の銅鐸が発見され、出土品は島根県立古代出雲歴史博物館に保管されています。出土した銅鐸は、国宝に指定されています。
銅鐸出土地のすぐ傍には、遺跡周辺の豊かな自然景観を楽しみながら遺跡への理解を深めることのできる総合案内施設「加茂岩倉遺跡ガイダンス」があります。[14]荒神谷遺跡(こうじんだにいせき)
1984年~1985年の発掘調査で、荒神谷遺跡からは、358本の銅剣が出土しました。当時、全国で出土した銅剣を全部あわせても300本余りだったため、この大量の銅剣の発見は当時の日本古代史学・考古学界に大きな衝撃を与えました。
日本最多の銅鐸が発見された加茂岩倉遺跡とわずか3.4kmしか離れていないことや、両遺跡からの出土品に同じ「×」印の刻印があることから、両遺跡は関係があるとみられています。
荒神谷遺跡 http://www.kojindani.jp/about/remains
日本最多の銅鐸が発見された加茂岩倉遺跡とわずか3.4kmしか離れていないことや、両遺跡からの出土品に同じ「×」印の刻印があることから、両遺跡は関係があるとみられています。
荒神谷遺跡 http://www.kojindani.jp/about/remains
[15]須佐神社(すさじんじゃ)
出雲風土記によると、スサノオが「この国は小さいけれどよい国なり、我名を岩木にはつけず土地につける」と仰せられて大須佐田、小須佐田と定められ、自分の御魂をこの地に鎮められたということです。
境内には樹齢1200年を超えると言われる大杉があり、見ごたえがあります。
須佐神社公式HP https://www.susa-jinja.jp/
境内には樹齢1200年を超えると言われる大杉があり、見ごたえがあります。
須佐神社公式HP https://www.susa-jinja.jp/
[16]出雲大社
縁結びとして有名な出雲大社。大国主(オオクニヌシ)が祀られています。旧暦10月(神無月)には全国から八百万の神々が集まり神議が行われるため、出雲では10月を「神在月」と言います。
出雲大社 https://www.izumooyashiro.or.jp/
出雲大社 https://www.izumooyashiro.or.jp/
[18]日御碕神社
島根半島の西端に位置し、スサノオ(素盞嗚尊)とアマテラス(天照大御神)の兄弟をお祀りしています。社殿のすべてと境内の石造建築物も含め、国指定重要文化財とされています。
日御碕神社/出雲観光協会HP https://www.izumo-kankou.gr.jp/678
日御碕神社/出雲観光協会HP https://www.izumo-kankou.gr.jp/678